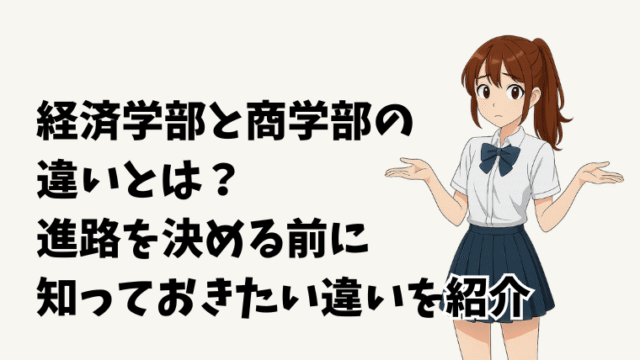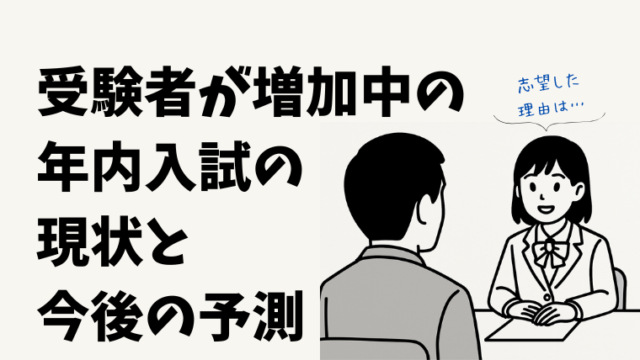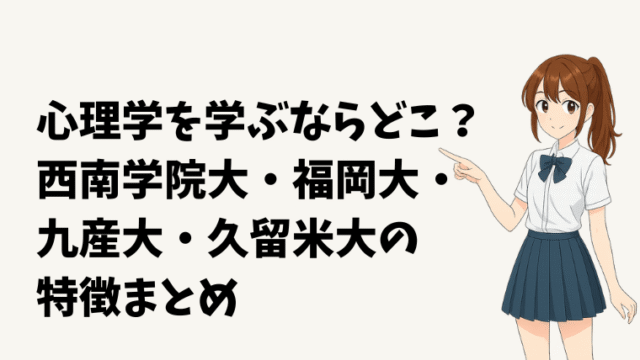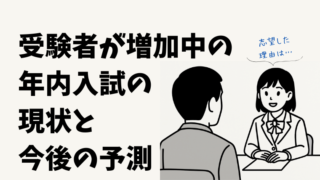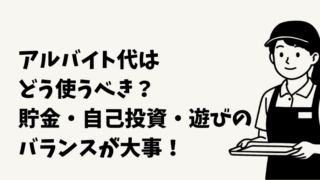大学の志望理由書に生成AIは使っていいの?メリットとリスク
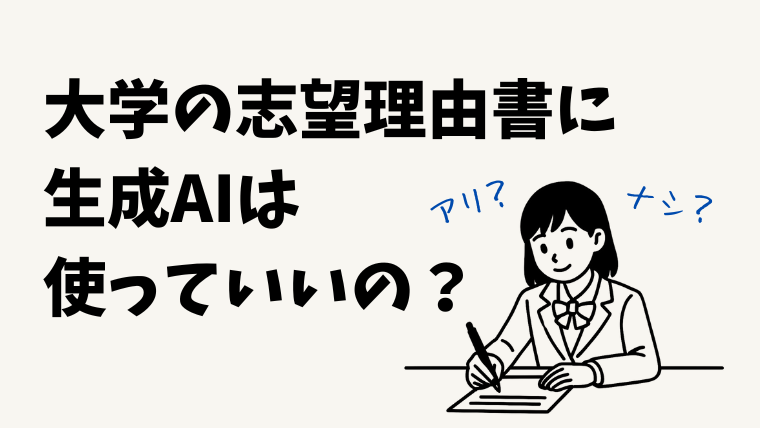
近年、ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AIの普及により、アイデア出しや調べ学習にAIを活用している高校生が増えてきました。
そんな中、多くの高校生や保護者が感じていることがあります。
志望理由書にAIを使うのはあり?なし?
今回は、志望理由書作成におけるAI活用の是非について考えてみましょう。
各大学で生成AI利用のガイドラインを決めている
明確に禁止している大学がある
まず知っておくべき重要なポイントは、大学によってはAIを使った志望理由書の提出を明確に禁止しているケースがあるということです。
総合型選抜、社会人選抜、学校推薦型選抜では、志望理由書などの出願書類の提出を求めております。この書類は志望する学部・学科への意欲、適性、能力などを評価するために大変に重要なものでありますから、AIを利用しての作成は認められません。 本学のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)や各学科が求める学生像を十分に理解した上で、自分の力(言葉)で書類を作成し提出してください。
出典:令和健康科学大学「志望理由書等の作成における『AI』の利用禁止に関する注意」
AIの使用が禁止されている大学に対して、それを隠してAI生成の文章を提出することは「不正行為」とみなされる可能性があります。
このような行為が発覚した場合、最悪のケースでは合格取り消しなどの厳しい措置が取られることもあるため、必ず志望大学のルールを確認しましょう。
志望理由書にAIを使うのはあり?なし?
各大学は学生向けに生成AIに関するガイドラインを定めているから、参考にした方がいいかもね。
AIを使うメリットとリスク
メリット:アイデア整理のサポート
生成AIは、自分の考えを整理する「思考のパートナー」として活用できます。例えば、「なぜこの学部を志望するのか」という問いに対して、自分では気づかなかった視点を提示してくれることがあります。
また、文章構成のアドバイスをもらったり、表現を磨いたりする際にも役立つでしょう。
特に文章を書くことに苦手意識がある高校生にとって、AIは心強い味方になりえます。
AIに色んな視点からアイデアをもらうってことね!
AIと対話を通して、自分の興味・関心を見つけるのは良いと思う。
リスク:個性の喪失と判断力の低下
しかし、AIに頼りすぎると、自分自身の個性や本音が薄れてしまうリスクがあります。
特に志望理由書は、「あなた自身」を評価する重要な材料です。
AIが生成した文章では、あなたの本当の魅力や熱意が伝わりにくいと思います。
AIと対話を通して、自分の興味・関心を見つけるのは良いと思う。
AIは私の”熱意”には勝てないってことね!
そう。多少、文章力が低くても、説得力が全然違うよ。
また、常にAIに依存していると、自分で考え、判断する力が育ちにくくなります。
大学生活では自分で考えて行動する場面が増えるため、この力を高校生のうちから養っておくことが大切です。
AI活用の「正しい」方法
サポートツールとして活用する
AIに「丸投げ」するのではなく、あくまで自分で気づけなかった自分自身の考えを発掘したり、文章作成を助けたりするツールとして位置づけるのが理想的です。
例えば以下のような使い方が考えられます:
- アイデア出しの補助:商学部に関するキーワードを出してもらう
- 自己理解のための補助:マーケティングに興味を持ったきっかけを一緒に考えてほしいといった相談をする
- 構成の相談:「志望理由書はどのような構成にするといいですか?」と聞いてみる
- 表現の提案:「この文章をより説得力のある表現に変えてください」と依頼する
最終的には自分の言葉で書く
どんなにAIを活用するとしても、最終的には自分自身の言葉で書き直すことが重要です。
AIの文章をコピー&ペーストするのではなく、AIからのアドバイスや提案を参考にしながら、自分の体験や思いを反映させた文章に仕上げましょう。
特に「なぜその大学の学部を選んだのか」という点については、オープンキャンパスでの体験や調べた内容など、自分自身の具体的なエピソードを盛り込むことで説得力が増します。
AIは私の”熱意”には勝てないってことね!
産まれてから今まで、全く同じ人生を送っている人はいないもんね!
自分の言葉で書くってことが一番大事だよ
AI時代の志望理由書作成のポイント
大学進学の本質を見失わない
AI技術がどれだけ発展しても、大学進学の本質は「自分が何を学び、どう成長したいか」を明確にすることにあります。
志望理由書を書く過程は、自分自身と向き合い、将来を考える貴重な機会です。
AIに頼ることで、この自己探求のプロセスを省略してしまわないよう注意しましょう。
大学面接対策においても、自分自身の言葉で語れる内容を準備することが重要です。
自分で書いたはずの志望動機を言えないってことは…
AIに書いてもらったか、先生や親に書いてもらったってこと?
AIは私の”熱意”には勝てないってことね!
AIは私の”熱意”には勝てないってことね!
面接官の立場からすると、そう言わざるをえないよね。
最後に(アドバイス)
生成AIに関するガイドラインを公表している大学が多く、生成AIのリスクについて懸念を示していたり、生成AIの使用を禁止したりする大学もあります。
ただ、これは私の個人的な意見ですが…
AIをうまく使いこなせる生徒の方が、将来、活躍できるのでは?
むしろ、AIをうまく活用できない人は置いてけぼりにあうのでは?
と思っています。
10年後には、生成AIなくては生きていけない時代が来ると私は思っています。
そんな中、生成AIの使用を禁止するのは時代遅れではないでしょうか。
もちろん、メリットもデメリットもあるので、うまく使いこなしましょう!
頼りになる先輩くらいの気持ちで使っていくといいのかもね!
まずは自己理解を深めるために使うといいかもね。